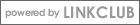August 31, 2006
リース会計問題の早期解決を(その2)
そもそも、リース取引は、なぜこれほど多くの上場企業において利用されているのでしょうか。私が考えるに、利用者にとってのリース取引のメリットとは以下のようなものではないかと考えています。? 資産を取得する場合に比べて初期投資額を抑えることができる。
? 固定資産の法定耐用年数より、リース契約期間を短く設定することにより、資産を取得する場合に比べて損金処理を早く行うことができ、節税になる。
? 実質的に借入金で資産を取得して利用する場合と経済的実態は同じであっても、貸借対照表にリース資産・負債を計上することを避けること(オフバランス化)ができる。
ただ、前回の記事で指摘したとおり、?は、日本特有のおかしな事象ではありますが、少なくともプロの投資家や債権者は貸借対照表本表だけを見て投融資を決定することはなく、注記情報は当然見ています。従って、例えば、日本航空の財務状況がリース注記情報を加味するとかなり悪いということは、当然に承知の上でプロ投資家、債権者は投融資を実行しています。このことを考慮すると、まともな会社であれば、リース契約のオフバランス効果のみに着目して、取得よりリースを選好することはありえませんし、リース会計基準の変更でリース資産・負債のオンバランス化が義務付けられたからといって、夕刊フジに記載されているような株価暴落による大混乱などが起こるはずがないと私は思っています。
それでは、なぜ、リース会社がこれほどまでにリース会計基準の変更に反発しているのでしょうか。私は、その理由が、?のリースの節税効果が実質的に使えなくなることにあると思っています。
そもそもユーザーにとって、本来のリース契約のニーズは?の理由にあるはずです。すなわち、資金繰りにそれほど余裕のない会社が、金額の大きな設備投資を割賦払いのような形で行うことができるというものです。この一時的な資金の負担をリース会社に肩代わりしてもらうからこそ、借入利息相当額を上回るかもしれないリース料を支払うことにメリットがあるわけです。このメリットを享受している企業にとっては、背に腹は変えられないわけで、リース会計基準が変更になるからといって、新規契約を取りやめることなどはできないわけです。
これに対して、?の効果に着目してリース契約を選好している企業は、リース会計基準の見直しによって、新規契約の見直しを図る可能性はおおいにあります。
現行の法人税法上、ファイナンス・リース契約の当初リース期間は、当該リース資産の法定耐用年数の70%以下(耐用年数が10年以上の場合は60%以下)の期間にしてはいけないという規定があります。これは、リース資産の契約期間を意図的に短くして、リース料を増加させることで、当該資産を取得して法定耐用年数で減価償却をする場合より、早く損金化して節税を図ろうという脱法行為を防止するためのものです。しかしながら、裏を返せば、70%(60%)までの期間短縮は認められるわけで、実際にこの節税効果をフルに活用している高収益企業も多いわけです。例えば、耐用年数10年以上の巨額の設備投資をリースで行うとなると、この40%の耐用年数短縮による節税効果(期間トータルで支払う税金は一緒ですが、損金化を早くして課税を繰り延べることも通常節税と言います。)は極めて大きくなります。
リース会計基準が改正されて、ファイナンス・リースのオンバランス化が強制されることになると、現行の法人税法上は、各企業は、リース物件を固定資産として計上し、法定耐用年数をもとに算定される減価償却費相当額の損金化しかできなくなると考えられます。その結果、リース契約による節税メリットはほぼ消滅することになるため、リース契約の節税効果に着目していた企業ほど、リースを選好するインセンティブはなくなります。これが、リース会社の契約獲得活動にとって大問題なのだと思われます。
リース会社にしてみれば、?の理由で必然的にリースを必要としている企業は、金利を高く設定するとしても、貸倒リスクも高いといえます。これに比べ、節税効果を活用したいような高収益企業とのリース契約は、たとえ金利が安く設定させられたとしても、ほぼノーリスクで手数料を稼げるのは魅力的です。この魅力的な顧客が減少することは、耐え難いため、「リース会計基準の改正は企業の設備投資意欲を低下させる可能性があるため、経済活性化にとってマイナスだ!」とか、「リース会計基準の変更に合わせた法人税法の改正が不可欠だ!」といった趣旨のことを発言されているのだろうと思います。
もともと節税メリットという「国の補助金」のようなものを積極的に援用してアピールするサービスの販売戦略は、他業種企業との競争を考えた場合、課税の公平性を欠くような事態になりかねないため、私はあまり望ましくないものと考えます。だとすると、今回の会計基準の改正に伴い、リース契約の節税メリットが消えることは、むしろ経済全体にとってフェアな状態に移行するので、歓迎すべきことなのかもしれません。
日頃、規制緩和を推し進め、フェアな経済社会への移行を積極的に支援している宮内会長あたりに、ぜひ、「リース会計基準の改正は当然行うべき」という趣旨のオトナの発言をしていただければと思う今日この頃です。
06:56:49 |
cpainvestor |
|
TrackBacks
August 27, 2006
リース会計問題の早期解決を(その1)
探検隊1995さんが、リース会計の問題について、「多くの過剰債務企業が危機的状況に陥るのではないか」とあの「夕刊フジ」にまで掲載されていることをレポートしてくれています。それでは、まず、現行の日本のリース会計基準の問題点について、私なりに簡単に解説します。なお、以下では、リース取引のユーザー(リース物件の借り手側)に立って話を進めていきます。
現行の会計基準上、リース取引は、大きく分けてまず、二つの種類に区分された上で、会計処理が定められています。
ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」といいます。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引を言います。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とはファイナンス・リース取引以外のリース取引を言います。
ファイナンス・リース取引については、お金を第三者から借りてきて、そのお金を使って自社で固定資産を購入する取引と実質的に同様であるとして、売買処理(資金の借入返済・とリース物件の購入、減価償却を行う会計処理)を行うことが原則です。また、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借処理(毎年、契約で定められた支払リース料を費用として処理する)を行うことが定められています。
これで会計基準の記述が終わっていれば、何の問題もなかったわけですが、実際には、ファイナンス・リース取引については、例外規定が設けられています。
ファイナンス・リース取引のうち、リース物件の所有権が借り手に移転していると認められないもの(いわゆる所有権移転外ファイナンス・リース取引)については、オペレーティング・リース同様の賃貸借取引による会計処理を認め、そのかわりに、売買処理をした場合に認識される情報の注記(リース物件の取得原価相当額、簿価相当額、減価償却費相当額、未経過リース料期末残高相当額、支払利息相当額など)を義務化しています。表向きは、多くの企業の「事務処理の簡便化に配慮する」ために例外規定を設けたことになっているようですが、実際にはリース業界の猛烈な反発により、賃貸借取引+注記という形に落ち着いたことは想像に難くありません。
ファイナンス・リース取引のほとんどが、契約書上はリース会社に物件の所有権が存在する形になっていますので、「所有権移転外リース取引」として、賃貸借処理+注記の会計処理が行えることになります。このため、実際には、例外であるはずの賃貸借処理が、大半の上場企業で採用されています。ただ、注記するために、売買処理を行った場合に算定される数値(リース物件の取得原価相当額、簿価相当額、減価償却費相当額、未経過リース料期末残高相当額、支払利息相当額など)が必要となるため、ご丁寧に多くのリース会社が、自社リース物件に関するこの必要情報を自ら計算してユーザー企業に提供してくれています。
この例外処理が認められていることで、この処理を採用している企業では、本来貸借対照表に計上されるべきリース資産とリース債務が計上されない(オフバランス化される)こととなるため、原則処理を採用している企業と比べて、貸借対照表のサイズが小さく見えますし、自己資本比率、総資産利益率(ROA)などの指標も良く見えます。また、リースの契約期間とリース物件の会社が定めた耐用年数が異なれば、同一企業においても、資産が取得されるかリースされるかによって毎期の費用計上額(減価償却費or支払リース料)が異なり、期間損益が歪められることになります。これらの論点が、投資家に誤解をもたらせる可能性があるため、問題だとされているわけです。
ちなみに、米国会計基準では、1976年という早い段階で「リースの会計処理」(FAS13:Accounting for Leases)が定められており、日本基準(1993年制定)の言うファイナンス・リースに該当する取引は、Capital Leaseとして明確に定義され、売買処理が求められています。(もちろん、例外はありません)
実務上、日米両国で上場している企業において、双方の基準に基づく2種類の財務諸表を作成している場合には、(通常は日本基準の財務諸表を作ってから、修正仕訳を入れて米国基準の財務諸表を作成します。)このリース会計の違いによる修正仕訳が、手間もかかってえらく大変だったりします。その理由は以下の通りです。
? 日本の財務諸表の開示ルールでは、リース契約総額が3百万円未満のリース契約は注記しなくて良いという規定があります。このため、特に3百万円未満のリース契約の状況に関してきちんと管理していない会社も多いですが、米国会計基準では、そのような記載はなく、細いリース契約も吸い上げなくてはいけなくなるので集計に手間がかかります。当然連結子会社全てです。
? また、毎年毎年、累積的に日米の財務諸表の数値が異なるので、その原因理由をタイムリーに整理記録しておかないと翌年の修正仕訳の一部が行えなくなります。
このため、米国SECの規制を受けている企業の経理や監査の現場での実害も、それなりに大きいと思われます。最近では、NY証券取引所やNASDAQに上場する企業は、米国会計基準で作成された連結財務諸表に、若干日本の会計基準に基づく連結財務諸表で要求されている補足情報を加えることで、日本の会計基準に基づく連結財務諸表を一から作成することが免除されていますが、ご丁寧に売買処理されているリース取引の会計処理を賃貸借処理に戻している企業もあるようです。
(つづく)
01:07:14 |
cpainvestor |
|
TrackBacks
August 02, 2006
コンテンツの会計処理は各社まちまち
映像、音楽、アニメ、ゲームなどの「コンテンツ」に関しては、日本には明確な会計基準が存在しません。このため、各社の処理は温度差があり、会計上の残された大きな課題のひとつとなっています。古くからのコンテンツビジネスであった映像、音楽などに関しては、法人税法上の償却規定があるため、関係各社はこれを意識しながら1年もしくは、2年以内の償却が行われてきました。会計実務上は、映像制作、音楽原版制作のコストは、仕掛品、前払費用などの資産勘定に計上し、発売時に一括売上原価として処理することが多いようです。
受託制作ではないアニメ、ゲームについても、会計実務上は、仕掛品勘定やコンテンツ勘定に制作費を資産として積上げておき、発売時に一括費用計上という会社が多いようです。
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」によれば、ゲームのように市場販売目的のソフトウェアとコンテンツが一体不可分として明確に区分できない製品の場合には、その主要な性格がソフトウェアかコンテンツかを判断してどちらかにみなして会計処理せよという規定がありますが、それ以上、コンテンツについては何ら記載がありません。
例えば、ゲーム会社の会計処理の例をとっても各社まちまちの対応です。某関東歴史系ゲーム会社のようにほぼ全額を制作時の費用として処理する会社もあれば、関西格闘系ゲーム会社のように制作時は仕掛品として資産に計上しておいて、販売時に費用化する会社もあります。両社の会計処理を比較すると、会計上の費用の認識のタイミングが大きく異なるため、業績の企業間比較がまったく意味をなさないことになります。
企業は当然ながら販売見込みがあるからこそ、コンテンツを制作するわけですが、これがヒットするかしないかは、まったく水物で、収益の不確実性は極めて高いといえます。
会計上「一定期間の成果(収益)獲得のために払った犠牲(費用)は対応表示すべき」という原則があるため(費用収益対応の原則)、販売可能性のあるコンテンツを制作している限り、これを資産計上することに一定の合理性はあるわけですが、なんでもかんでも資産に計上しておいて、販売見込みがなくなったので除却しますと突然多額の除却損を計上されるのは、いくらCFには影響がないとはいえ、正直投資家としてはかないません。
コンテンツ産業は、その制作に時間がかかることが多い上、資金回収はいくつもの手段(映像コンテンツの例で言えば、放映権販売、映像配信収入、DVD販売など)を介して行われるため、本当に単年度決算がなじまない業態だと思います。ただ、財務安全性を考慮すると、コンテンツ別の費用収益対応原則が遵守できなかったとしても、なるべく保守的に早期に費用計上しておくことがより望ましいと思います。(ただ、税法上は認められない費用計上であることも多いのが難点です。税金は先払いしなくてはならないからです。)
投資家としては、やはり、多額のコンテンツ資産を資産計上している場合には、近づかない方が無難かもしれません。やはり複数年度の営業CF、投資CFの推移で会社の状態を判断するしかないようです。
ただ、投資家のためにも、早くある程度統一的かつ包括的なコンテンツに関する会計基準を作ってもらいたいと思う今日この頃です。
17:27:28 |
cpainvestor |
|
TrackBacks